あと数日で8月ですね。
夏の暑さもそろそろ折り返し…になるかなぁ(汗)。
小中学校も夏休みに入り、放デイには朝から子供たちが来ています。
仕事自体は楽しいのですが、生活リズムの変化と忙しさで、アミのHPはかき氷のようにゴリゴリ削られております。
さて、前回の記事では、仕事がうまくいかない原因について「できる仕事」と「やりたい仕事」という視点からお話してきました。
今回は、その解決編として、発達障害当事者に取り組んでほしいこと、職場・発達障害当事者を雇う人に協力してほしいことについて書いていきたいと思います。
発達障害当事者が取り組むこと ~就活中の人向け~
まずは、
「面接をたくさん受けているけど、内定をもらえない」
「働きたいけど、どんな仕事をすればいいの?」
という人に取り組んでほしいことです。
◎自分の「できる仕事」と「やりたい仕事」を正しく知る
まずはこれが一番大事!
「できる仕事」は何か? 「やりたい仕事」は何か?
「できる仕事=やりたい仕事」なのか、「できる仕事≠やりたい仕事」なのか?
ここが自分でわかっていないと、面接などで自分をうまくアピールできません。
この辺をうまく整理するためには、自分で考えるだけよりも、周囲の力を借りたほうが近道になると思います。
発達障害がある人は、自分のことを客観的に見ることが苦手な人が多いです。
なので、一人で悶々と考えてドツボにはまる前に、周囲の力をうまく借りましょう。
例えば、こんな方法があります⇓⇓
・信頼できる家族や友人に相談する。
・障害者職業センターに相談する。
・相談支援事業所に相談する。
・就労選択支援を利用する。
◎働きたい会社の「やってほしい仕事」を知る
面接などを受けて内定をもらうためには、会社が「やってほしい仕事」を知って、「やってほしい仕事=できる仕事」になるような会社を見つける必要があります。
また、「やってほしい仕事=できる仕事」であることを会社に知ってもらうことも必要です。
そのためのサポートを受けられる場所は次の通りです⇓⇓
・お住いの自治体で行われている、公共の就労サポート
(例:東京都→東京しごと財団 障害者就業支援事業、宮城県→障害者就業・生活支援センターなど)
・民間の就職エージェント
(障害者の就職に特化:LITALICO仕事ナビ、デイゴー求人ナビ、ランスタッドチャレンジドなど)
(一般就労向け:doda、マイナビエージェント、リクルートエージェントなど)
・就労選択支援(主に就労継続支援A型・B型を目指す人向け)
◎「やってほしい仕事」「やりたい仕事」を「できる仕事」にする
働きたい会社は見つけたけど、「やってほしい仕事≠できる仕事」だった…
「できる仕事≠やりたい仕事」だけど、「やりたい仕事」を諦めたくない!
そんな時は、「やってほしい仕事」「やりたい仕事」を「できる仕事」にできるようスキルアップを目指しましょう。
・ハロートレーニング(障害者訓練):ものづくり、PCスキル等、ハードスキル(仕事に直結するスキル)を身に着けたい人向け。
・就労移行支援:ハードスキルに加え、生活習慣や対人マナーなどソフトスキル(仕事を長く続けるために必要なスキル)も身に着けたい人向け。
発達障害当事者が取り組むこと ~現在働いている人向け~
続いては、今現在雇われて働いている人の中で
「頑張って働いているのに、評価してもらえない」
「つまらない仕事ばかりで、やる気が出ない」
「なぜか仕事が長続きしない、いろんな職場を転々としている」
というような人に取り組んでほしいことです。
◎自分の「できる仕事」と「やりたい仕事」を正しく知る
まず最初に取り組んでほしいことです。
自分では「できる仕事」だと思ってやっていても、実際はただの「やりたい仕事」で、職場で力を発揮できていない可能性があります。
逆に、自分にとっては当たり前すぎることが、実は「できる仕事」につながることもあります。
それを知るためには、自分一人で考え込むより、周囲の人の力を借りたほうが近道になると思います⇓⇓
・信頼できる上司や同僚に相談する。
・ジョブコーチ制度を利用する。(詳しくは各都道府県の障害者職業センターへ)
◎働いている会社の「やってほしい仕事」を知る
自分の「できる仕事」「やりたい仕事」が分かったら、次は今働いている会社・上司が「やってほしい仕事」は何か?を確認しましょう。
もし、「やってほしい仕事=できる仕事」であれば、あなたはきっと職場から必要とされているはずです。
利用できるサポート⇓⇓
・信頼できる上司や同僚に相談する。
・ジョブコーチ制度を利用する。
◎「やってほしい仕事」を「できる仕事」にする
前の2つの項目を確認して、もし
・「やってほしい仕事≠できる仕事」ではなかった
・でも、今の仕事をまだ続けたい
という場合は、「やってほしい仕事=できる仕事」になるような工夫をしましょう。
そのための方法は、「何ができるようになりたいか?」によって違いますが、例えばこんな方法があります⇓⇓
・信頼できる上司や同僚に指導してもらう。
・書籍やYoutubeなどを利用して、独学で身に着ける。
・社会人向けのセミナーや通信教育などを利用する。
◎「やってほしい仕事」「できる仕事」の中から「やりたい仕事」をみつける
「やってほしい仕事=できる仕事」だったけど、それに対してやる気がわかない…という場合の対策です。
といっても、書くのは簡単ですが、これを実践するのがなかなか難しいんですよね。
発達障害(特にASD)で興味関心の偏りや白黒思考などが強く出ている場合、「やりたい仕事」から目をそらすことがとても苦しい・つらいことのように感じてしまいます。
でも、「生活のために働かなきゃいけない」など、仕事を辞めたくない理由があるなら、今の職場で「やりたい仕事」を探す価値はあると思います。
具体的な取り組み方はこちら⇓⇓
・信頼できる上司や同僚、家族、友人などに相談する。
・ジョブコーチに相談する。
・現在やっている仕事をリスト化して、その中で「やりたい仕事ランキング」を作る。
・最終的には、自分でよく考えて納得できる答えを見つける。
◎自分の「できる仕事=やりたい仕事」で働ける職場を探す
ここまでの方法を全部試してみて、「やっぱり今の仕事はしんどい、続けられない」という場合の最終手段です。
「やってほしい仕事=できる仕事=やりたい仕事」になるような職場に転職しましょう。
ただ、「100%理想の職場」はほぼないという割り切りも必要です。
どんな職場に行っても、「やりたくない仕事」や「苦手な仕事」が1つ2つは必ずあります。
給料や労働時間、人間関係などに不満を感じることもありえます。
「40点の職場」から「60点の職場」に転職できればOK!くらいの気持ちで取り組めるといいと思います。
利用できるサポートは次の通りです⇓⇓
・お住いの自治体で行われている、公共の就労サポート
(例:東京都→東京しごと財団 障害者就業支援事業、宮城県→障害者就業・生活支援センターなど)
・民間の就職エージェント
(障害者の就職に特化:LITALICO仕事ナビ、デイゴー求人ナビ、ランスタッドチャレンジドなど)
(一般就労向け:doda、マイナビエージェント、リクルートエージェントなど)
・就労選択支援(主に就労継続支援A型・B型を目指す人向け)
職場の方に協力してほしいこと
職場で、発達障害がある部下や同僚と関わる中で、
「頼んだ仕事をやらずに、他の業務をやりたがる(やっている)」
「 “こういう仕事をしたい” “自分はこんなことができる” と話しているが、実力が全く伴っていない」
「仕事に対してやる気がないように見える」
といったことはありませんか?
もしかしたら、会社側の「やってほしい仕事」と本人の「できる仕事」「やりたい仕事」のすり合わせが十分にできていないかもしれません。
本当なら、自分で考えて何とかするところかもしれませんが、発達障害の特性上、自分や周囲の状況を正しく理解することが難しいケースもあります。
そこで、「発達障害当事者もできる限りのことをする」という前提で、同じ職場で働く皆さんに協力してほしいことがあります。
◎発達障害について正しく知る
◎その人の「得意なこと」「苦手なこと」「好きなこと」「嫌いなこと」を知る
◎「得意なこと」「好きなこと」を活かせる仕事を任せる
◎できるだけ、「苦手なこと」「嫌いなこと」が少ない環境にする
◎改善してほしいところは、根気強く伝え続ける
◎必要に応じて、障害者職業センターの「事業主援助業務」など、外部の支援サービスを利用する
発達障害がある人は、関わり方にコツがいる場合もありますが、「得意なこと」「好きなこと」を活かして働ければ、きっと大事な戦力になるはずです。
このブログでも、発達障害について知るためのコンテンツを発信していきます。
まずは「正しく知る」ところから始めてみてください。


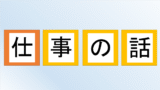

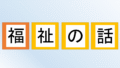
コメント