令和7年8月4日、仙台市急患センターのホールで「仙台っ子健康セミナー」が開催されました。
平成26年から年1回のペースで開催され、今年で11回目のこのイベント。
毎年、運動や食生活、睡眠など、健康や子供の成長に関する講演が行われてきました。
主に、学校の教職員や、子育て中の保護者向けに行われているようですが、一般の人も参加できます。
仙台市教育委員会が主催で、なんと参加料は無料!

今回、アミもこのセミナーに参加してきたので、講演を聞いて感じたことなど、書いていきたいと思います。
講演① 「やる気を引き出す言葉」
講師:阿部和子氏(一般財団法人 日本ペップトーク普及協会)
「ペップトーク(PEP TALK)」についての講演でした。
ペップトークとは、ポジティブな言葉かけをすることで、相手のやる気を引き出す方法のことです。
反対に、ネガティブで相手の意欲をそぐような言葉かけを「プッペトーク」と言うそうです。
なんと、あのメジャーリーガー大谷翔平も、ペップトークの考え方を実践しているとか…!
「事実をあるがまま受け入れる」
「物事をプラスに捉える」
「してほしい行動を具体的に伝える」など…
今回、ペップトークという言葉は初めて知りましたが、内容としては、普段療育現場で実践していることが多かったです。
言葉かけの大切さを再確認することができ、「子どもとの関わり方、今の方針で続けて大丈夫そう!」と自信を持つことができました。
ただこの方法、実践する大人にも気持ちの余裕がないと、なかなか大変なんです…
忙しかったり、疲れていたりして気持ちに余裕がないと、どうしてもマイナスな部分に目が向いてしまいがち。
アミの職場(放課後等デイサービス)は現在、絶賛繁忙期(泣)。
子どもたちのいい所をたくさん見つけられるように、「余裕のある大人」でいたいです。
実践発表 「校舎建て替えによる校庭減少に伴って予想される体力低下を防ぐ取組について」
発表者:麻生信行氏(仙台市立黒松小学校 校長)
仙台市立黒松小学校での2年間の取り組みについて、聞くことができました。
黒松小学校では、
「校舎の建て替え工事に伴い、校庭が狭い状態が続いている」
「体力運動能力検査で、仙台市の平均を下回る項目が多い=運動が苦手な児童が多い」
という課題を解決するための、様々な取り組みをしてきたそうです。
その取り組みの中で、ステキだな、と感じたのが、
「階段の踊り場に運動用具を設置して、子どもたちが自由に使えるようにした」
というもの。
「校庭がない=運動できない」
ではなくて、
「使えるスペース・使えるものをフル活用」
と発想の転換をしているところ。
それに加えて、階段の踊り場という子どもたちが必ず通る場所を有効活用することで、子どもたちが自主的に体を動かすようになる、そういう仕組み作りがとてもいいな、と思いました。
私の職場では、「子どもたちが前向きな気持ちで療育に取り組むには、どうすればいいか?」が話題になることがあります。
子どもたちが「この活動、面白そうだからやってみたい!」と感じて自主的に参加してもらえるような、そんな仕組み作りをしていきたいな、と思いました。
講演② 「健やかな子どもの体・脳・心のための食と栄養」
講師:伊藤明子氏(赤坂ファミリークリニック 院長)
食事と栄養の大切さについての講演でした。
タンパク質、鉄、亜鉛、ビタミンDなど…
食べ物であふれた現代日本でも、こういった栄養素が足りていない人が多いこと。
栄養素が足りないせいで、気持ちや身体が不健康になったり、発達に悪影響が出たりすること。
目から鱗なお話ばかりでした。
講演の中で、善玉菌と食物繊維を摂ることで花粉症の症状が軽くなる、というお話がありました。
アミは、2~3年前から米こうじから発酵あんこ・塩こうじ・醤油こうじを作って食べるようになりました。
中学生の頃からスギ花粉の花粉症があったのですが、ちょうどその頃から花粉症の症状がほぼ出ていないな…と講演を聞きながら気が付きました。
栄養と健康って、本当につながってるんだ!と思いました。
どんな食品を、どうやって食べれば必要な栄養が摂れるのか、もっと深掘りして知りたいですね。
まずは先生の著書を読んでみようかな。
そして自分の食生活を見直して、ゆくゆくは調理レクなどを通して療育にも活かせたらいいな、と野望を持っています(笑)。
講演③ 「なぜあの人は健康行動しない?~ナッジで行動へと促す~」
講師:竹林正樹氏(青森大学 客員教授)
行動経済学の「ナッジ」という方法について、お話を聞くことができました。
「勉強しなきゃいけないのは分かるけど、ついゲームをしてしまう」
「節約しなきゃいけないのは分かるけど、つい衝動買いをしてしまう」
「禁煙しなきゃいけないのは分かるけど、ついたばこを吸ってしまう」
そんな「分かっちゃいるけどできない」ことの原因を、行動経済学の言葉で「認知バイアス(認知のゆがみ)」と言うそうです。
その認知バイアスをうまく利用して、「自然と望ましい行動をしてしまう」状況を作るのがナッジ!
講演の中では、代表的な認知バイアスやナッジについて教えてもらうことができました。
理論的なところも分かりやすくて、「具体的にこうしてみよう!」というお話もあって、大満足な内容でした。
職場で療育をする時にも、ナッジを取り入れられれば、子どもたちが自然とプラスな行動をする環境を作れそうだな、と期待が高まりました。
竹林先生(通称:ちくりん博士)のYoutubeでも、ナッジの具体的な使い方を知ることができます⇓⇓
まとめ
今回、1日を通して4つの講演を聞いてきた感想、一言で言うなら
大・満・足!!!
こんなに内容の濃いお話を、無料で聞ける機会は中々ないな、と思いました。
でも、限られた時間の中でのお話だったので、正直まだまだ聞き足りない!
本を読んだり実践したりして、もっと深く知っていきたいな、と思っています。
仙台市では、今回の講演のような学びの場がたくさんあるので、今後もアンテナを張って、できる限り参加していきたいです!

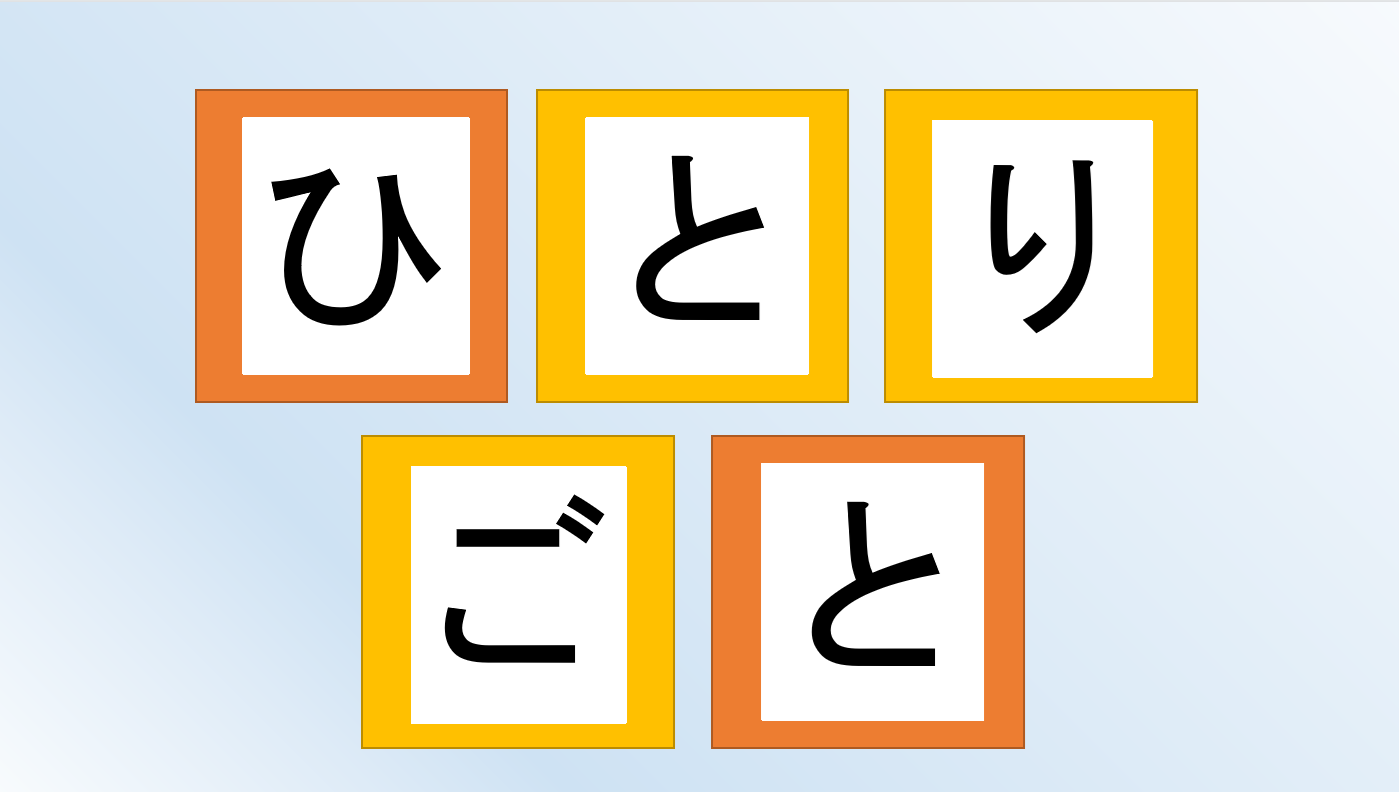
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4953af34.7b494e42.4953af35.2e691119/?me_id=1213310&item_id=21455537&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9180%2F9784065369180.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4953af34.7b494e42.4953af35.2e691119/?me_id=1213310&item_id=21465957&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3005%2F9784418253005_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4953af34.7b494e42.4953af35.2e691119/?me_id=1213310&item_id=20817555&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5091%2F9784478115091.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4953af34.7b494e42.4953af35.2e691119/?me_id=1213310&item_id=21049641&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3792%2F9784594093792_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4953af34.7b494e42.4953af35.2e691119/?me_id=1213310&item_id=21414771&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8149%2F9784479798149.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
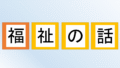
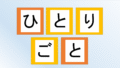
コメント