今回も、私の発達障害の特性についてお話していきたいと思います。
前回までは、アミの弱み・苦手なことを書いてきましたが、今回は強み・得意なことについてです。
アミの特性(ASD、ADHD)
1.聴覚過敏
2.空気が読めない(相手の状況や気持ちが読み取れない)
3.日本語のリスニングが苦手
4.初めての状況(特にアクシデント)が苦手
5.融通が利かない
6.話すペースが遅い、雑談が苦手
7.時間管理が苦手
8.片付けが苦手
9.コツコツと積み重ねることが得意(「人との信頼関係」は例外)
10.知識の習得が得意
11.情報収集が得意
12.文章や図表で伝えることが得意
今回は、9.10.11.12.について書いていきます。
◎コツコツと積み重ねることが得意(「人との信頼関係」は例外)
事務作業や療育グッズ作り、仕事や資格取得のための勉強などを、地道にコツコツ積み重ねていくことが得意です。
体力的に、集中して一気に終わらせることは難しいのですが、そのぶん細く長く続けています。
STの資格を取る時は、過去問を解くことと、自分専用の参考書・暗記ツールを作るために、毎日コツコツと積み重ねていました。
ファイナンシャル・プランナー(FP)2級の資格を取る時も、3級を取るのに1年、2級を取るのに1年、合計2年間、細々と勉強を続けてきました。
資格の学校TACでは1~2か月、ユーキャンでは3~5か月を資格取得の目安としているようなので、かなり時間をかけています。
見方によっては「要領が悪い」等、マイナスイメージになってしまうかもしれません。
でも、人より体力がなく疲れやすい、時間管理も苦手という状態で、たとえ人より時間がかかったとしても、一度始めたら投げ出さずに続けられるところは長所と言えるかな、と思っています。
ただし、人との信頼関係については、コミュニケーションの苦手さからコツコツと関係を築くことが難しく、卒業や転職などで関係が終わってしまうことが多いです。
◎知識の習得が得意
教科書などの本を読んで知識を吸収する、いわゆる「お勉強」は学生の頃から得意分野でした。
興味がある分野限定ですが、もっと知りたいという知識欲が強いことや、コツコツ続けるのが得意なこと、知能検査の結果から言語性の知能が平均よりも高いことなどが要因でしょうか。
私の場合、知識を丸暗記や語呂合わせなどで覚えることはとても苦手だったのですが、学生時代、あまり興味がない教科は丸暗記で乗り切ろうとしてしまい、何度か痛い目を見ています。
一方で、自分の持っている知識やこれまでの体験と結び付けて覚えることは得意で、さらに興味のある分野については積極的に勉強していたので、たくさんのことを吸収できました。
社会人になってから、特に放デイで働き始めてからは、自分の興味がある分野を仕事にできているので、療育や障害者の自立に関することを積極的に学んでいます。
FP2級の資格は今年に入ってから取りましたが、きっかけは、障害者の自立を考えるためにお金の知識も必要だと考えたからです。
◎情報収集が得意
気になることがあると、気が済むまでとことん調べます。
何を調べるかにもよりますが、調べるツールはネットや書籍が多いです。
休日に参加できそうな研修会などがあれば、参加することもあります。
調べた後は、調べ切った満足感に浸って終わることもありますが(特に趣味についての調べ事の場合)、仕事に関することは、できるだけ職場で実践したり発信したりするようにしています。
◎文章や図表で伝えることが得意
集めた情報を文章でまとめることが得意です。
仕事柄、患者さんやお子さんの様子を文章で記録したり、リハビリや療育の方針を文書にしたりといったことを続けてきたので、文章を書く機会は多くありました。
また、仕事の一環として人前で発表をする機会が何度かありましたが、私にとって発表本番にアドリブで話すことは結構ハードルが高いです。
たとえ、「大体こんな感じのことを話せばいい」という大筋が分かっていても、です。
その対策として、発表本番で何をどんな言い回しで話すか?という原稿を、事前に作るようになりました。
そうすることで、どんな言い方をすれば伝えたいことが伝わるか、時間配分は適切かなどを落ち着いて考えられるようになりました。
図表で伝える力は、人前で発表をするためにパワーポイントで資料を作ることで鍛えられました。
図表は、細かくて緻密なものよりも、パッと見て全体が分かるようなものを作れるよう意識していて、「分かりやすかった」と言ってもらえることもあります。
私は耳から入る情報よりも目から入る情報のほうが得意なので、文章で伝えることも、図表で伝えることも、特性と合っていたのだと思います。
ここまで、4回に分けて私の特性について書いてきました。
発達障害の特性がある人全員が、私と同じ特性を持っているわけではありません。
それでも、発達障害について知るためのひとつのツールとして、何かしら感じ取っていただければ幸いです。


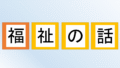
コメント