先日、「仙台っ子健康セミナー」でナッジを知り、もっと詳しく知りたいと思って竹林先生の著書を読んでみました。
Gakkenから出版されている「介護のことになると親子はなぜすれ違うのか ナッジでわかる親の本心」という本です。
どんな本?
この本は、高齢の親にどうやって必要な介護サービスを利用してもらうか、ということをテーマにした本です。
本の中には、8組の親子が登場します。
「介護を受けたくない親と、介護サービスを利用してほしい子」
「子ども夫婦に介護をしてほしい親と、必要に応じて公的なサービスも利用してほしい子」
など、状況は様々ですが、そんな親子の困りごとを「ナッジ」を使って解決していきます。
「ナッジ」の理論とか、抽象的なアドバイスではなく、具体的な声掛けのしかたが紹介されているので、「これならできそう!」と思わせてくれます。
さらに、読んでいて感じたのは、「高齢者介護だけじゃなく、障害者福祉の現場でも、こういう場面ってあるあるだな」ということです。
必要と思われる福祉サービスについてご提案しても断られてしまったり、障害のある方本人に現状を正しく認識してもらうことが難しかったり…
そこで、今回と次回の記事では、この本の内容を元にして、障害者福祉(特に発達障害)の場面でどのように応用できるか、考察していきたいと思います。
「認知バイアス」と「ナッジ」
「認知バイアス」と「ナッジ」は、今回のテーマを語るうえで超重要なキーワードです。
「認知バイアス」というのは、多くの人に見られる行動パターンのことです。
普段生活していて、「○○するべきなのは分かってるのに、つい××してしまう…」という経験はありませんか?
そんな「理性と違う行動」をしてしまう原因が「認知バイアス」です。
「認知バイアス」は行動経済学という分野で研究されていて、人間の考え方や行動にどんなパターン(認知バイアス)があるのかが、かなり詳しくわかってきました。
一方で、「認知バイアス」は「今やるべきこと」に取り組みやすくするために使うこともできます。
そのための方法が「ナッジ」です。
「認知バイアス」をうまく利用して、「やるべきこと」を「ついやりたくなること」に変えてしまいます。
ついやりたくなるので、「無理矢理やらされた」というやらされ感がありません。
「認知バイアス」というのは、定型発達の、大多数の人にも当てはまる行動パターンですが、その中には発達障害の特性とよく似ているものもあります。
そこで今回は、代表的な6つの認知バイアスと、発達障害の特性との類似点をご紹介したいと思います。
※あくまでも「類似点」であり、「認知バイアス=発達特性」ではありません。
損失回避バイアス
定義:利益を得るための行動より、損失を避けるための行動を優先してしまう。
類似点:
ASDの人は予期しない変化や失敗を強く避ける傾向があるため、「損をしない」ことを優先する行動が出やすい傾向があります。
ADHDでも、ネガティブな経験を強く記憶しているため、それを避ける行動を選びがちです。
→ どちらも、損失や失敗を過大に評価して行動選択に影響する点が似ています。
現状維持バイアス
定義:新しい選択肢より、現状維持という選択肢を好む傾向。
類似点:
ASD特性では、「慣れた手順や環境を変えたくない」というこだわりが強い傾向があります。
ADHDでも、新しい手順や環境に慣れるまでは計画力や実行機能に負荷がかかるため、「現状維持のほうが楽」と感じる傾向があります。
→ 新しい選択肢に、気持ちの面で抵抗を感じやすい点が似ています。
投影バイアス
定義:今の感情や状況が将来も続くと過信する傾向。
類似点:
ASDでは、柔軟に考えることが苦手なため、将来の多様な可能性を予測するより、今の状態が将来も続くと考えてしまう傾向があります。
ADHDでは、「今」の感情が何よりも優先されやすいため、将来の見通しを冷静に考えて判断することが難しい傾向があります。
→ 現在の感覚や気分が、未来予測を不正確にする点が似ています。
自信過剰バイアス
定義:自分の判断や能力を実際以上に高く見積もる傾向。
類似点:
ASDでは、得意なことや興味があることの能力を高く評価しすぎて、他の苦手なことを見落とすことがあります。
ADHDでは、「今これをやりたい」という気持ちの強さからリスクを過小評価し、自分ならできると思い込みやすい傾向があります。
→ できることに目が向きがちで、苦手なことに気が付きにくいところが似ています。
現在バイアス
定義:将来のメリットよりも、目の前の利益を重視する傾向。
類似点:
ASDでは、強いこだわりや興味があると、その活動をすることが最優先になり、「今やるべきこと」を後回しにしがちです。
ADHDでは、「将来のメリット」が手に入るまで待つことが難しく、すぐ得られる楽しみを優先しがちです。
→ どちらも「目の前の利益」に引っ張られやすい傾向があります。
利用可能性バイアス
定義:すぐに思い出せるものを過大評価して判断する傾向。
類似点:
ASDでは、強く記憶に残っている過去の出来事や、自分の興味があることが、物事の判断基準になる傾向があります。
ADHDでは、最近の経験や、今の強い感情が、物事の判断基準になる傾向があります。
→ 色々な情報を組み合わせて判断するより、思い出しやすさや印象の強さに影響されて判断するところが似ています。
ここまで、代表的な「認知バイアス」と発達障害との関係について説明してきました。
次回の記事では、具体的にどんな困りごとが起こるのか、「ナッジ」を使った解決方法について書いていきたいと思います。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4953af34.7b494e42.4953af35.2e691119/?me_id=1213310&item_id=21222342&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2436%2F9784058022436_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

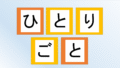
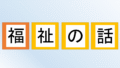
コメント